「毎日の腸活をもっと美しく、もっと健康に。」をコンセプトに
【美腸ラボ】を運営しています、YAKOといいます!
あなたは、便秘・下痢・便もれなどの腸トラブルに悩んだことはありませんか?
これらの腸トラブルは、生活習慣が密接にかかわっているといわれていますが
生活習慣を改善するひとつの手段として
よい便のもととなる「食物繊維」を上手に摂る
ということが大切になります
この記事では
・いい便を出す方法を知りたい
・腸をすっきりキレイにしたい
という人のために
「腸トラブルを解消する!毎日いい便を出すための食物繊維の取り方5選」を解説します
食物繊維とは?「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」
食物繊維には
水に溶けて便のすべりをよくする「水溶性食物繊維」と
水に溶けず便のかさを増やす「不溶性食物繊維」の2種類があります
それぞれ違った特徴や効果があるので
両方ともバランスよく摂ることが大切です
「水溶性食物繊維」の特徴と効果
「水溶性食物繊維」は、水に溶けるため
硬い便を柔らかくする(バナナ状のうんちに近づける)とともに
粘液(ベタベタ、ネバネバした液)となって便のすべりをよくし
便秘解消に役立ちます
「水溶性食物繊維」は、大腸内で腸内細菌である「善玉菌」のえさになり
「善玉菌」を増やします
「水溶性食物繊維」は、腸内でのコレステロールの吸収を妨げ排便を促すだけでなく
糖質の吸収速度を穏やかにするので
脂質異常症や糖尿病の予防に効果があるといわれています
1.便を柔らかくする
2.便の形を整える
3.「善玉菌」のえさになる
「不溶性食物繊維」の特徴と効果
「不溶性食物繊維」は、水に溶けず
水分を吸収して、便のかさを増やし
「蠕動運動」を促したり、便の形を整えたりします
また、水分と一緒に老廃物などの余分なものを吸収しながら腸内を進むため
腸内をキレイにする効果があります
1.便のかさを増やす
2.「蠕動運動」を促す
3.腸内をキレイにする
食物繊維を摂るときのポイント5選
食物繊維を摂るときポイントを5選、紹介します
「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」は
それぞれ特徴と効果が異なるため
両方ともバランスよく摂ることが大切です
いずれの食物繊維も、加熱するとかさが減って、柔らかくなるので食べやすくなります
また、特に「不溶性食物繊維」は、他の栄養素と違って、消化・吸収されにくいため
よく噛んで、胃腸に負担をかけないようにしましょう
食物繊維は、いろいろな食材に含まれるので
ひとつの食材をたくさん食べるより、食材数を増やして食べたほうが
栄養がかたよりにくくおすすめです
食物繊維は、食品のみで摂る限りでは、過剰摂取の心配は少ないですが
サプリメントなどで一度に多量に摂ると、下痢を起こすことがあります
また、鉄やカルシウム、亜鉛などの吸収を妨げるため
ミネラル不足になることがあります
1.「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」の両方をバランスよく摂る
2.加熱すると、かさが減り柔らかくなって食べやすい
3.特によく噛んで、胃腸に負担をかけないようにする
4.いろいろな種類の食物繊維を摂る
5.サプリメントなどでは、摂り過ぎに注意して不足分のみを補う
おすすめの食物繊維一覧を紹介
食物繊維を多く含む食材は
「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」のどちらも含んでいることがほとんですが
いずれかを多く含む食材と、どちらも多く含む食材があります
「不溶性食物繊維」が多い食材(可食部100g)
きくらげ(乾)・・・57.4g
干ししいたけ・・・46.7g
きなこ・・・16.9g
干し柿・・・14g
いんげんまめ・・・13.6g
ゆで大豆・・・6.6ℊ
モロヘイヤ・・・5.9g
ブロッコリー・・・4.4g
しいたけ(菌床)・・・4.2g
玄米ご飯・・・1.4g
「水溶性食物繊維」「不溶性食物繊維」のどちらも多く含む食材(可食部100g)
切り干し大根(乾)・・・21.3g
オートミール・・・9.4g
乾燥バナナ・・・7g
納豆・・・5.9g
ごぼう・・・5.7g
アボガド・・・5.3g
海藻に含まれる食物繊維(可食部100g)
海藻類は、強い粘りが生じるため、不溶性と水溶性の分別分析が難しいためといわれています
ひじき(乾)・・・51.8g
焼きのり・・・36g
わかめ(乾)・・・32.7g
昆布(乾)・・・27.1g
-1.jpg)
季節ごとに摂るといい旬な食材
旬な時期に取れた食材は
値段がお手頃で手に入りやすいだけでなく
栄養価が高く、その季節に必要な栄養が摂れるといわれています
食物繊維を多く含んだ、季節ごとに旬な食材をご紹介します
夏・・・オクラ・モロヘイヤ・とうもろこし
秋・・・さといも・かぼちゃ・さつまいも・れんこん
冬・・・ほうれん草・ごぼう・白菜
.jpg)
食物繊維は一日にどれくらい摂ればいい?
「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、下表のように目標値が定められています
引用元:「日本人の食事摂取基準(2025年版)」厚生労働省
成人女性では、1日に18g以上を食事から摂取しましょう!
また、「不溶性食物繊維」:「水溶性食物繊維」=2:1で摂取するのが理想的です
・不足した場合・・・便秘、腸内環境の悪化
・摂り過ぎた場合・・・下痢、ミネラルの吸収阻害
・食事摂取基準・・・【成人男性:22g以上/日 成人女性:18ℊ以上/日】
【まとめ】食物繊維の上手な摂り方
食物繊維を上手に摂ることで、腸トラブルを解消し、腸内環境を良くするだけでなく
様々な健康効果が期待できます
いろいろな種類の食物繊維を摂ることを心がけましょう
・不足した場合・・・便秘、腸内環境の悪化
・摂り過ぎた場合・・・下痢、ミネラルの吸収阻害
・食事摂取基準・・・【成人男性:22g以上/日 成人女性:18ℊ以上/日】
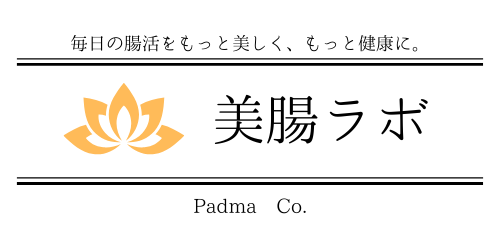






2025.png)

コメント